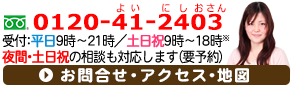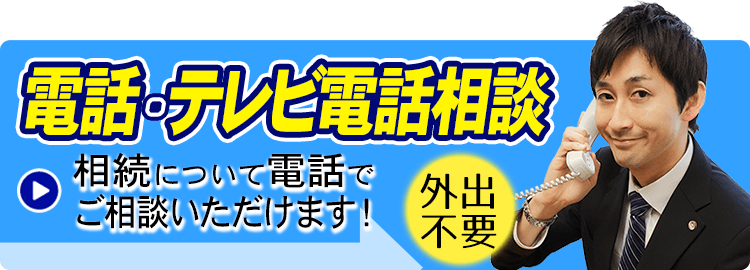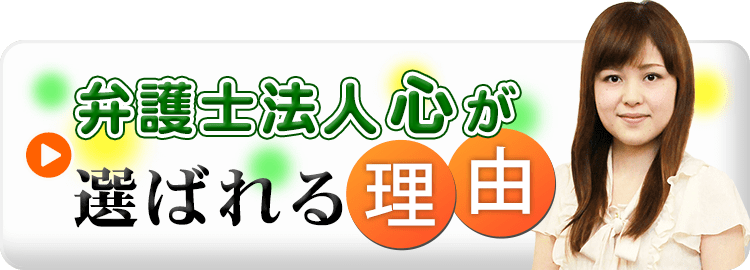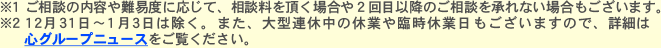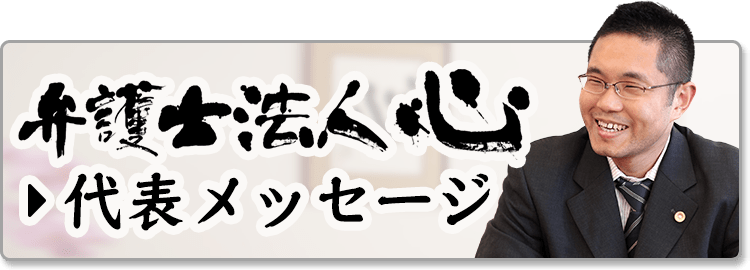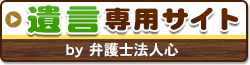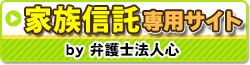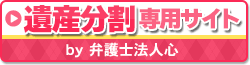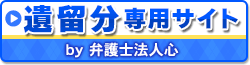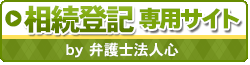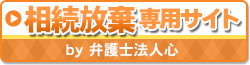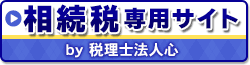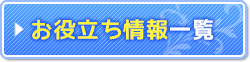遺産分割調停の流れ
1 家庭裁判所への申立て
相続人の間で遺産分割の協議ができない場合には、遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
裁判所には地方裁判所や簡易裁判所、高等裁判所などがありますが、遺産分割調停を申し立てるのは家庭裁判所です。
ただし、どこの家庭裁判所でも申し立てられるわけではなく、遺産分割調停の管轄があるのは相手方となる者の住所地の家庭裁判所です。
たとえば、相手方の住所地が岐阜市であれば、岐阜家庭裁判所に管轄があります。
相手方のうちの一人でもその裁判所に管轄があれば、その裁判所で調停をすることができます。
そのため、たとえば、相手方のうち一人でも岐阜市に住所があるのであれば、他の相手方が遠方であったとしても、岐阜家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
そのほかに、当事者で合意した家庭裁判所でも調停をすることができますので、当事者全員が都合がよいと考える裁判所でも調停をすることができます。
2 申立てに必要な書類
⑴ 申立書
遺産分割調停を申し立てるためには、申立書を作成する必要があります。
申立書の書式は、各家庭裁判所の窓口で取得することができるほか、ホームページでも取得できます。
申立書を作成したら、相手方の人数分の写しを作成して、裁判所に提出します。
相手方の人数分の写しが必要になるのは、申立ての後、これらが相手方に郵送されるからです。
調停の申立てについての案内をしている裁判所のホームページもご参照ください。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停
⑵ 戸籍などの相続関係書類
申立てでは、相続人が申立書に記載された当事者ですべてであることを確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書)、相続人全員の戸籍謄本のほか、被相続人と相続人の関係に応じて必要となる戸籍を提出する必要があります。
また、相続人の住所が分かる住民票や戸籍の附票も、申立書の写しを郵送する際の宛先を確認するために提出する必要があります。
⑶ 遺産に関する資料
相続人に関する書類のほかに、遺産に関する資料を提出する必要があります。
遺産に不動産がある場合には、不動産の内容を確認するための登記事項証明書や、不動産の価値を把握するための固定資産税評価証明書を提出する必要があります。
不動産の評価額を固定資産評価額と異なるものとして主張する場合には、不動産会社の査定書等の資料を提出することになります。
遺産に預貯金がある場合には、亡くなった時点や現在の残高が分かる資料として、通帳の写しや金融機関が発行する残高証明書を提出する必要があります。
これらのほか、遺産の中に、株式や投資信託などの金融資産、組合への出資金やゴルフ会員権などがあれば、これに関する資料を提出する必要があります。
⑷収入印紙と郵券
遺産分割調停を申し立てるには、1件について1200円分の収入印紙を提出することが必要です。
このほかに、連絡用の郵便切手を提出する必要がありますが、どのような額面の切手が、それぞれ何枚必要かは、各家庭裁判所によって、調停の当事者の数によって異なりますので、裁判所のホームページを確認するか、裁判所に問い合わせてください。
3 調停の流れ
調停では、2人の調停委員と1人の調停官によって構成される調停委員会が遺産分割の仲介をします。
当事者は、裁判所から指定された期日に裁判所に出頭し、申立人と相手方が交互に調停室に入って、自らの考えを述べることになります。
通常、調停官は、同時に複数の事件を受け持っているため、当事者の前には出てこず、男女1名ずつで構成される調停員が当事者の話を聴きます。
当事者が弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理人として調停に参加することができますが、弁護士らの代理人を除いて、当事者以外の者が調停に参加することはできません。
調停の基本的な進め方は、相続人や遺産の範囲についての争いがないかを確認した後、寄与分や特別受益などの具体的相続分を修正する主張の有無や、その内容を整理し、遺産の分割方法についての主張を確認することになります。
通常、一度の期日で調停が成立することはありません。
そのため、それぞれの期日で、主張内容の整理や証拠の提出など、次回期日までの宿題やその後の段取りを確認して、次回期日に臨むことになります。
調停の途中で、それまでに争いがないことが確認できたり、争いがある事項について部分的な合意ができたりする場合には、中間合意をしたうえで、その後の調停を進めていくこともあります。