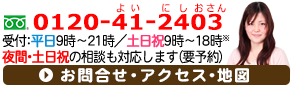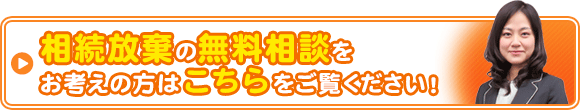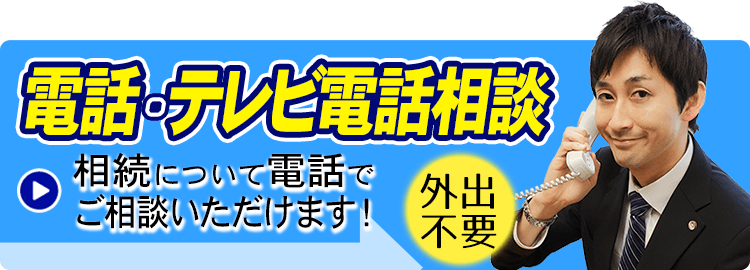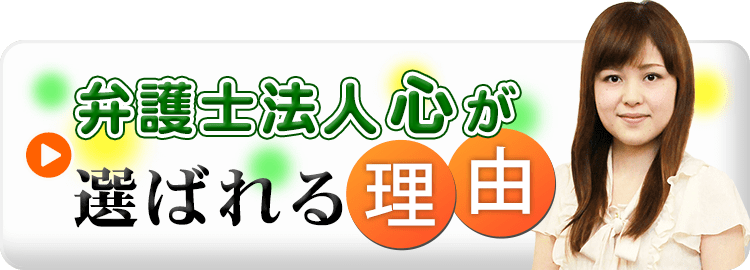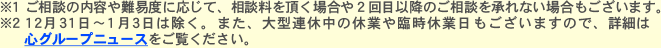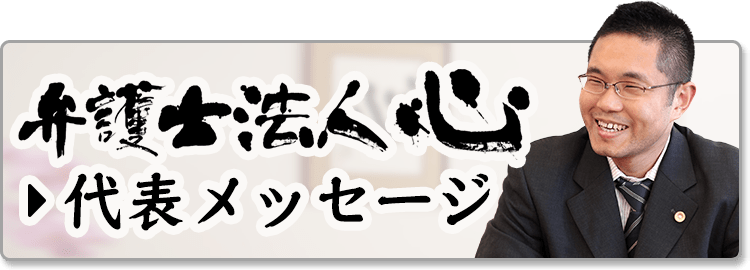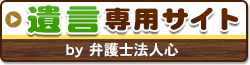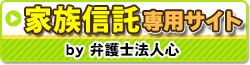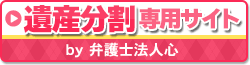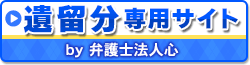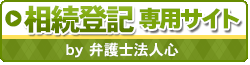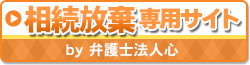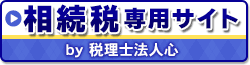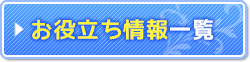相続放棄と限定承認の違い
1 相続放棄は相続財産を承継しないが、限定承認は相続財産を承継する場合がある
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を相続しないことを法的に認める制度をいいます。
そして、相続人が相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとされ(民法939条)、その後相続人は、被相続人の権利義務を一切承継しないこととなります。
例えば、被相続人が1億円の借金を残してお亡くなりになった場合であっても、相続放棄をしてしまえば相続人は1億円を返済する義務を免れることができます。
例えば、被相続人が1億円の借金を残して亡くなった場合、権利義務を承継した相続人は、1億円の借金を返済する義務を負います。
しかし相続放棄をしてしまえば、相続人は1億円を返済する義務を免れることができます。
他方、限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務等のマイナスの財産を相続すること法的に認める制度をいいます。
その結果、限定承認をした相続人は、プラスの財産からマイナスの財産を引いた時に、残額が残っていればその残額について権利義務を承継し、残額がないのであれば超過したマイナスの財産の義務を免れることができます(民法922条)。
例えば、被相続人の財産が1000万円で、負債が900万円であった場合、相続人は1000万円から900万円を引いた残額の100万円について権利行使することができます。
また、被相続人の財産が1000万円で、負債が1100万円であった場合、相続人は1000万円から1100万円を引いた際の100万円の残債務については、支払う必要はありません。
以上の性質から、相続放棄は一切の権利義務を承継しないのに対して、限定承認は残額がある時には権利義務を承継することになるという点に違いがあるといえます。
2 相続放棄はプラスの財産がないと分かっているとき、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産が分からないときに使う
相続放棄は、被相続人の権利義務を一切承継できなくなってしまうことから、被相続人の財産が債務超過状態であることが明らかなときに使用することが良いでしょう。
逆に限定承認は、被相続人の財産をプラスの財産の範囲内で承継できるので、被相続人の財産がどの程度あるのかわからないときに使用します。
例えば、プラスの財産が1000万円でマイナスの財産が900万円であることが明らかなときには、相続人は単純承認を行い、相続財産を承継したうえで900万円の支払いを行うことができます。
しかし、プラスの財産が1000万円だが、マイナスの財産が900万円~1100万円の範囲内だが確定できないという場合、相続人としてはマイナスの財産額を法的に決定できず、単純承認も相続放棄もできない状態になります。
そこで、マイナスの財産を確定するための手続きとして限定承認という手続きをとることが合理的となるわけです。
以上のことから、相続放棄はプラスの財産がないと分かっているとき、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産が分からないときに使うという点に違いがあります。
3 申請をすることができる当事者の範囲が違う
相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所に申し立てを行うことで手続きが開始します。
この場合、相続人が複数いても、その内の一人が相続放棄を行いたい場合には単独で相続放棄を行うことができます。
限定承認は、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行うことで手続きが開始します。
この場合、相続人が複数いた時に、一人でも限定承認に反対していれば原則として限定承認を行うことはできません。
例外的に、反対している相続人が相続放棄を行うのであれば、残った相続人のみで限定承認の申し立てができるようになります。
この場合、残った相続人は、反対している相続人が放棄したか否かを確認することができます。
この制度を、相続放棄の申述の有無についての照会といいます。
4 「相続人がいない場合の相続財産清算人」と「限定承認の際の相続財産清算人」は選任される者、弁済までの期間に違いがある
相続放棄の手続きを行った後、申立人以外に相続人がいる場合には、その相続人が申立人の権利を按分して承継します。
そして、完全に相続人がいない場合には、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により、相続財産清算人を選任しなければなりません(民法952条1項)。
この相続財産清算人は、通常弁護士や司法書士等の専門家が選任されることになります。
そして、家庭裁判所は遅滞なく相続財産清算人の選任した旨及び相続人がいるならば権利を主張すべき旨を最低6か月間公告し(同条2項)、その後に相続財産清算人が、債権者と受遺者に対して債権の申し出を行うように最低2か月間公告をすることになります(民法957条1項)。
この期間が満了した後に、相続財産清算人は債権者と受遺者に対して弁済をすることになります(同条2項、929条)。
したがって、債権者や受遺者は弁済を受けるまで最低でも8か月は待つことになります。
限定承認の手続きを行った場合は、申立人が1人の場合には、その1人が法律の規定に則り、プラスの財産の換価とマイナスの財産の支払いを行います。
しかし、申立人が複数の場合には、家庭裁判所が申立人の中から代表者を選出し、相続財産清算人としてプラスの財産の換価とマイナスの財産の支払いを行うことになります(民法936条)。
また、相続財産清算人は、限定承認後5日以内に、すべての債権者・受遺者に対して、限定承認をしたことと請求の申し出をすべきことを最低2か月間公告する必要があります(民法927条1項)。
このことから、債権者と受遺者は弁済を受けるまで最低でも2か月は待つ必要があります。
また、知れている債権者・受遺者には各別に催告をする必要があります(同条3項)。
これは、債権者に債権行使の機会を確保する趣旨の規定であり、この手続きを怠ると、それによって生じた損害を賠償する必要があります(民法934条)ので、気を付けましょう。
以上のことから、相続放棄をした後の「相続人がいない場合の相続財産清算人」と「限定承認の際の相続財産清算人」には選任方法と任務に違いがあります。