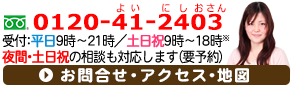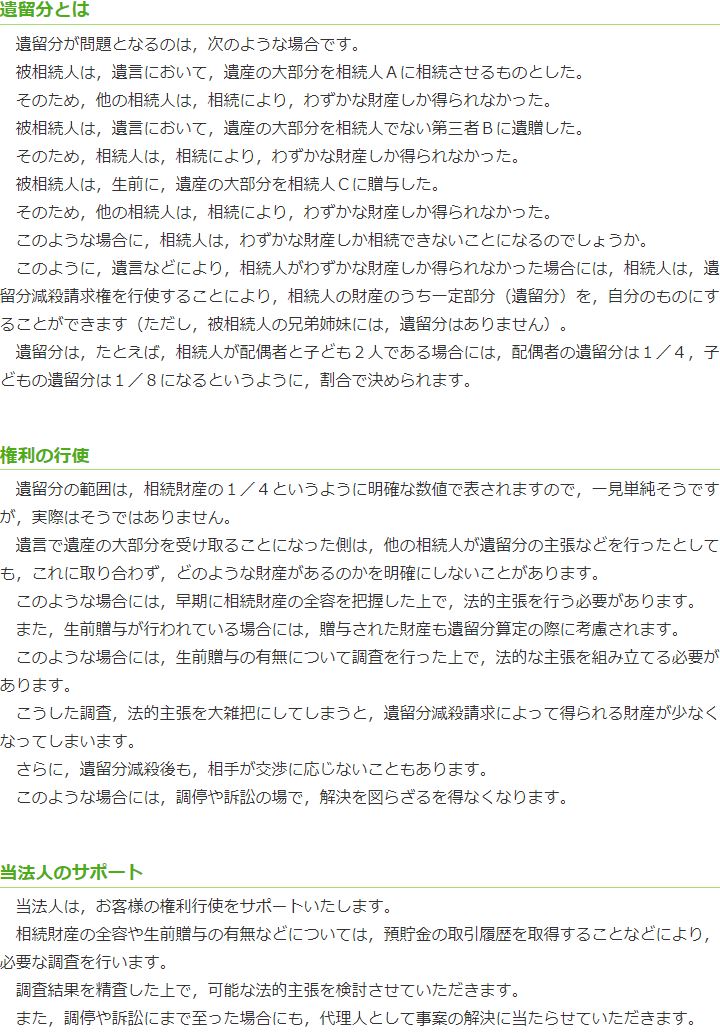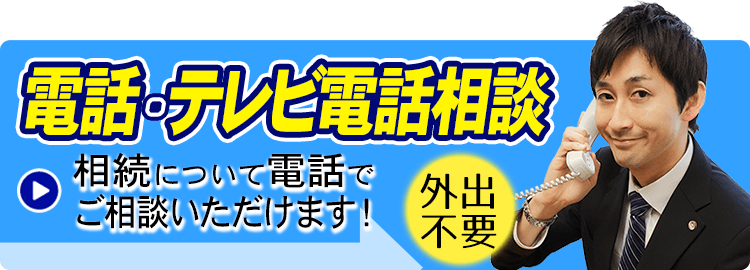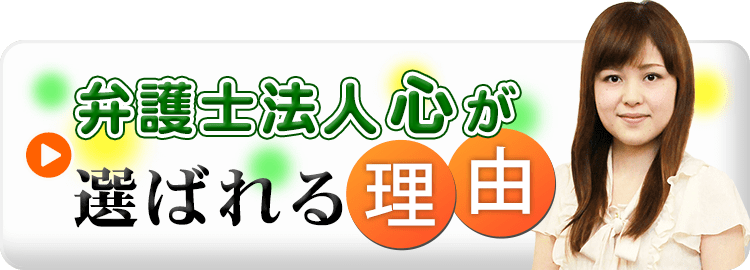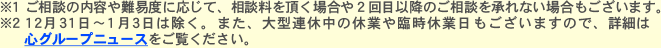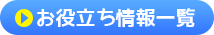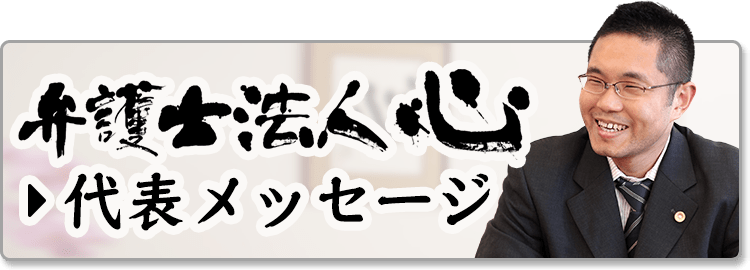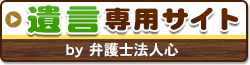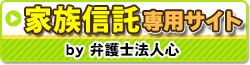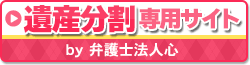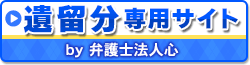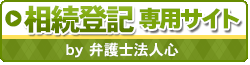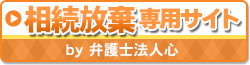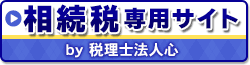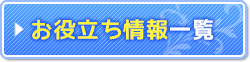遺留分侵害額請求
遺留分が問題となる具体例
1 遺産の分配が不均衡な場合

遺留分が問題となる典型事例としては、遺産の分配が不均衡な場合があげられます。
たとえば、父が亡くなり、相続人は長男と長女の二人だけであったところ、父が長男にすべての遺産を相続させる旨の遺言を残していたとします。
父の遺産は自宅不動産3000万円と預貯金1000万円であった場合、長女は、遺言によって遺産を受け取れなくなってしまうため、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
具体的には、長女の遺留分割合は4分の1であるため、長男や長女に生前贈与がなく、父に負債もない場合だと、長女の長男に対する遺留分侵害額請求額は、4000万円の4分の1の1000万円となります。
長男は、この遺留分侵害額請求額を現金で支払う必要があるため、遺産である預貯金から遺留分を支払ってしまうと、長男の手元には、自宅不動産のみが残るという結果になってしまう可能性があります。
2 相続人に生前贈与がある場合
遺留分が問題となる事例として、他にも、被相続人(亡くなった方)から相続人に生前贈与がある場合なども典型的な事例としてあります。
たとえば、父の財産として、自宅不動産3000万円と預貯金1000万円があり、父の相続人は長男と長女の場合、父が生前、長男に対し、自宅不動産を贈与したとします。
この場合、当該自宅不動産の贈与が、父が亡くなる前10年以内にされたものであった場合、原則として、遺留分の対象財産となります。
そのため、父の相続の際、父の遺産が預貯金1000万円のみであり、これを長男に相続させる遺言があった場合、長女は、預貯金1000万円の4分の1の250万円ではなく、預貯金1000万円と生前贈与3000万円を合わせた4000万円の4分の1である1000万円について、長男に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。
なお、長男は、父から自宅不動産を贈与される際に、贈与税や登録免許税、名義変更にかかる司法書士費用を支出した場合でも、これらの費用は基本的に考慮されませんので、注意が必要です。
3 遺留分についてはすぐに専門家にご相談を
遺留分については、1年の期限があり、これを過ぎてしまうと遺留分請求が認められない可能性があります。
また、遺留分請求額については、どの専門家に相談されるかによっても、請求できる金額が異なる可能性があります。
これは、遺産である不動産の評価や生前贈与の主張方法に関して、専門家ごとに知識や経験について、バラつきがあるためです。
そのため、遺留分についてご不安な方は、なるべく早めに、相続に強い専門家にご相談されることを強くおすすめします。