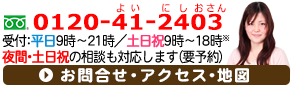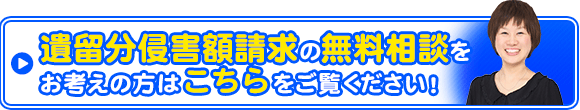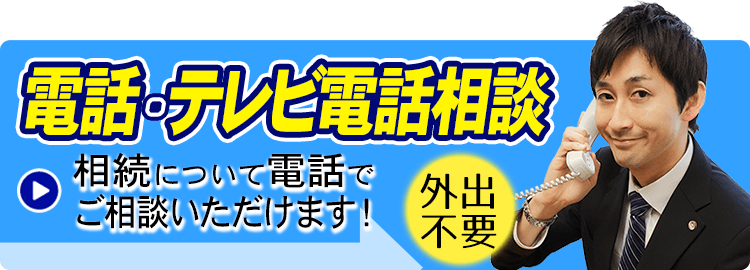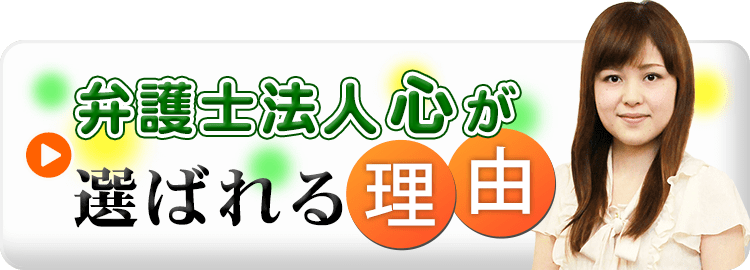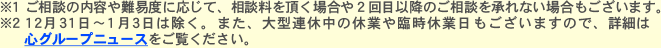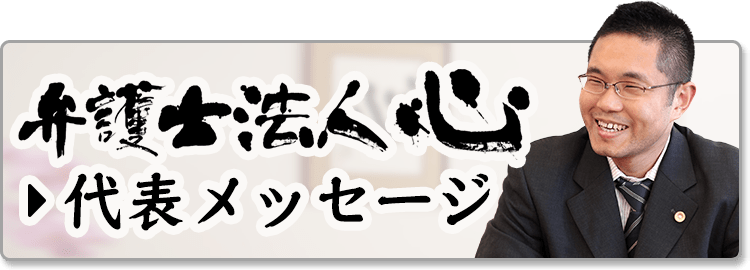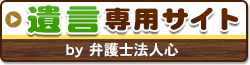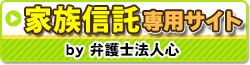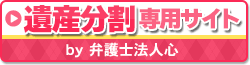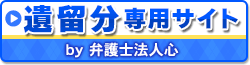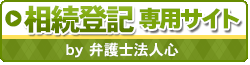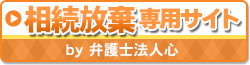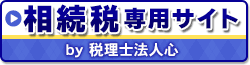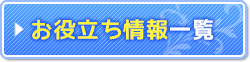遺留分侵害額請求権についてのQ&A
遺留分侵害額請求権とは何ですか?
遺留分侵害額請求権とは、亡くなった方が生前に贈与をしていたり、遺言で遺贈したりしたことで、法定相続人の一部の者の遺留分が侵害されていた場合に、その者から遺留分を侵害した人に対して、侵害した額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利のことをいいます。
平成30年の相続法の改正の際に、それまでの遺留分減殺請求権から権利の内容が変更され、遺留分侵害額請求権という権利になりました。
遺留分侵害額請求権が認められている相続人はだれですか?
遺留分侵害額請求権を行使することができるのは、法定相続人のうち、兄弟姉妹とその代襲相続人を除いた相続人です。
そのため、亡くなった方の配偶者や、子どもや孫、両親には遺留分がありますから、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
前提として、その者が相続人である必要があります。
たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合、両親はただちに相続人ではないため、遺留分はありません。
また、兄弟姉妹や甥姪には遺留分の権利は認められていません。
遺留分はどのようにして請求するのですか?
遺留分は、権利がある者から侵害をした者に対して、「いくら支払ってください」という形で請求をします。
通常は、以下で触れるように消滅時効等の問題がありますので、請求したことの証拠を残しておくために、内容証明郵便で請求することが多いです。
遺留分侵害額請求をするのに期限はあるのですか?
遺留分侵害額請求権には期限があります。
遺留分を請求する側が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
また、この期限に加えて、相続の開始から10年以内にも請求されている必要もあります。
この期限内に確実に請求をしなければなりませんし、後日、裁判などで請求したことの事実が争われた場合に備えて、請求したことの証拠を残しておく必要があります。
さらに、一度この請求をした後にも、通常の金銭債権と同じように、裁判上の請求などをしないと消滅時効にかかってしまうので、注意してください。
遺留分の請求できる金額はどのように計算するのですか?
遺留分の具体的金額は、遺留分を算定するための財産の価額に、遺留分割合を乗じ、請求者の法定相続分を乗じて計算することになります。
ここでいう遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1になります。
その後、請求者が亡くなった方から受けていた生前贈与や遺贈、遺産分割協議で取得した財産などがある場合には、これを控除する一方で、承継した相続債務がある場合にはこれを加算します。
どの時期になされた生前贈与が遺留分の対象になるのですか?
遺留分を算定するための財産に算定される生前贈与は、原則として、相続の開始前の1年以内の間になされたものが対象とされています。
しかし、相続人に対する生前贈与であれば、原則として、相続開始前の10年以内の間になされたものが対象となります。
当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときには、このような期間の制限はありません。
亡くなった方から受けていた生前贈与や遺贈、遺産分割協議で取得した財産などがある場合には、これを控除する一方で、承継した相続債務がある場合にはこれを加算します。
請求できる金額が決まった後は、誰にいくらの請求をすればよいのですか?
遺留分を侵害している受遺者や受贈者が複数いる場合には、それぞれに対する請求額を計算する必要があります。
まず、受遺者と受贈者がいるときには、受遺者が先に遺留分侵害額を負担することになっています。
そして、受遺者が複数いる場合には、遺贈の目的の価額に応じて遺留分侵害額を負担することとなっています。
受贈者が複数いる場合には、新しい贈与を受けた者から遺留分侵害額を負担することになっています。
いずれの場合も、その負担は自らが受けた遺贈や贈与の価額などが限度であるとされています。
このようにして計算された額を請求することとなりますが、上記のほかにも細かなルールがあるため、弁護士に相談されることをおすすめします。
遺言の種類についてのQ&A 相続放棄をしたら賃貸物件に住み続けることはできないのですか?